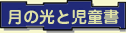 −私たちのなかの子どもへ− (25) −私たちのなかの子どもへ− (25) |
久保慧栞 |
アンネ・フランクが生きていれば
『アンネの日記』(著者:アンネ・フランク / 訳:深町真理子 / 出版社:文春文庫)
『床下の小人たち』(著者:メアリー・ノートン / 訳:林 容吉 / 出版社:岩波少年文庫)
『アナベル・ドールの冒険』(著者:アン・M・マーティン、ローラ・ゴドウィン /
絵:ブライアン・セルズニック / 訳:三原 泉 / 出版社:偕成社)
第二次大戦末期、『アンネの日記』を残し、ナチスの収容所で亡くなった少女、アンネ・フランク(1929-1945)。アムステルダムの隠れ家での窮屈な生活の果てに、家族ともども収容所に連行されました。作家になるのが夢だったというアンネは、本とバラに姿を変えて世界中に平和を訴えつづけています。
児童書を読んでいると、そんなアンネをほうふつとさせる出会いがあります。小さな人たちの暮らしを描いた古典シリーズ『床下の小人たち』。人間に見つからないよう床下に隠れ住んでいる「借り暮らし」の小人たちが、ふと、アンネの一家にかさなってきます。ここにも好奇心旺盛で本を読んだり日記を書いたりするのが好きな少女、アリエッティがいるのです。
そして、『床下の小人たち』への愛着が感じられる最近の作品『アナベル・ドール』のシリーズ。ここにもまた、人間には「物」として見えるよう、苦労しながら生きている、本好きのアナベルという人形の少女がいます。アンネ、アリエッティ、アナベル。みなイニシャルがAなのは興味深い一致です。
自分が指先ほどの小さな存在になって、ティーカップのそばに座っていたり、階段をよじのぼったりする様子を想像するのは楽しいですが、アリエッティやアナベルにとっては危険をともなう現実の世界です。アリエッティは人間に見つかったら住みなれた家を出て行かねばなりませんし、アナベルは場合によって「永久お人形状態」となり、死んでしまいます。
アンネにとっては言うまでもなく、見つかれば収容所行きを意味します。しかしアンネの場合は、同じ人間の手で死の宣告がなされたことは、アリエッティやアナベルには想像もつかないことでしょう。児童書の著者たちはアンネを想い、彼女たちに「生き延びた」アンネの姿を託したのかもしれません。
|


